|
かわらけ
かわらけは漢字で書くと土器という字があてられます。中世によく使われていた土器で、食器や儀式や祭祀(さいし)に使われていたものです。宴会(えんかい)などでは使い捨ての容器として利用されていたため、遺跡から出土するときにはまとまって出土することがよくあります。今でも簡単な宴会などでは、予算の関係や後片付けの問題などから紙コップや紙製のお皿などを用いる場合がありますね。ちょうどこの紙のお皿に近い使われ方をしていたんです。
その形は、器高(きこう=うつわの高さ)が高くて坏形(つきがた)をしたものや、お醤油のつけ皿のように低くて皿形をしたものなどがあり、大きさは8cm〜15cm位までさまざまあります。また、うつわの厚さは比較的薄いものが多いのですが、中には厚ぼったいものもあります。
写真にのかわらけは、横浜市金沢区にある国指定史跡称名寺(しせきしょうみょうじ)の古い伽藍(がらん)跡を発掘調査した時に出土したかわらけです。かわらけの口縁部に黒いタール状のものが付いているものが見受けられます。これは、このかわらけが灯明皿(とうみょうざら=油皿)として使用されたことを示しています。
電気のない時代には、室内の照明に灯明皿を用いていました。皿や浅い坏状のうつわの中に油をはり、芯になるものを差し入れ、その芯の先に火を着けて明かりとしていました。ちょうど理科の実験に使うアルコールランプのような原理です、分かりますか? このように芯と油を入れたかわらけを燭台のような台に載せたり、棒を結んで作った結び燭台に載せて照明として使っていました。この様子は12世紀の終わり頃に描かれた『餓鬼草紙(がきそうし)』や『病草紙(やまいのそうし)』などの絵巻物にも描かれています。また、時代が新しくなり江戸時代に入るとこの灯明皿の周りに木枠を組み紙を貼って行灯(あんどん)と呼ばれるようになります。
このような方法で明かりをとっていたため、芯の先端(火がついている部分)がかわらけの油の部分に接してしまうと、油が完全に燃焼しないでかわらけの表面に付着してしまうことがあります。そうです、実はあの付着物は油が変化した跡なのです。また、似たように見えますが、煤(すす)がついている場合もあります。
先ほど冒頭で、かわらけがまとまって出土する場合があることをいいましたが、浅い掘り込み(くぼみ)のなかに大量のかわらけが集まっていることがあります。こうしたものをかわらけ溜(た)まりと呼んでいます。
右側の写真は、称名寺の旧伽藍調査の時に検出したかわらけ溜まりです。まだ掘る前の写真なので分かりにくいですが、表面にはかわらけがいくつか見えています。この窪みはわずか20cmほどの浅い掘り込みでしたが、形状が分かるくらいに復原できたかわらけがなんと37個体も出土しました。この他にも接合できないかわらけの破片が見つかっていますので、1つの掘り込みの中にぎっしりと捨てられていたことが分かります。
さすがにこの場所はお寺の敷地の中なのでお酒を飲んだのではないのでしょうが、勉学に励んでいたお坊さんたちも勉強の合間にちょっとした宴会(やっぱり精進料理?)で息を抜いたのでしょうか。
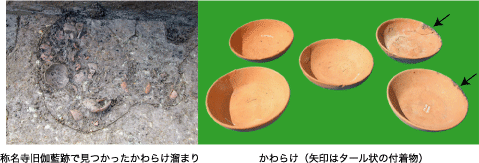
|
