 |
紡錘車について
昔の人たちは、どうやって糸を作っていたんでしょうか?
糸作りは、毛髪のように細く裂いた麻や樹皮(じゅひ)など植物の繊維せんいを、紙縒(こより)のように撚ることから始められました。その後、さまざまな道具を使うようになり、現在の紡績方法になりますが、今から約2,000年前頃の弥生時代では紡錘車という道具を使っていました。
紡錘車には土製や石製のものが多く、中には金属製のものもあります。その形状は、土製と石製のものは、その形状は、円錐形の上半部分を取り除いたような形、そう、例えていえば背の低いプリンのような形をしています。また、金属製は円板状を呈しています。また、素材にかかわらず、中央には必ず穴が穿たれており、この穴に棒状の紡茎(ぼうけい)と呼ばれるものを差し込んで使いました。また、弥生時代のものには土製・石製が多く、木製や鹿角(ろっかく)製のものもあります。古墳時代以降には鉄製のものがあらわれます。
紡錘車を用いた糸の紡ぎ方は次のようなものであったと考えられています。まず、糸を撚るための原料の繊維(せんい)の先端をあらかじめ紡茎に付けておきます。それから、どちらかの手で紡茎を立てます、そして、もう一方の手で繊維を指先でつまんで送り出します。この時に紡茎を回転させていきます。すると、元々あった繊維に撚りがかかって糸状になっていきます。そうして出来上がったものを紡茎に巻き付けていきます。この時に、単に紡茎を回すだけではうまく回すことができません。そこで、紡茎を回すときに反動をつけるための錘(おもり=はずみ車)をつけました。この錘の部分を紡輪(ぼうりん)と呼びます。
本来は、この紡茎との紡輪部分を含めたものを紡錘車といいます。しかし、発掘調査では紡茎の部分は腐ってしまい、紡輪の部分しか見つかりません。そして紡輪があたかも車輪のようにも見えることで、この紡輪の部分を誤って紡錘車と呼んでしまうことが多々あります。実際に博物館などの展示でもそう書いてあるものがあるようです。正式には紡錘車の紡輪と表記しないといけません。
糸を紡ぐ際には、海外においても同様の方法を用いていたことが分かっています。海外では、この紡錘車のことをスピンドルと呼んでいます。
アンデス地方の人たちが使っているタイプのものは軸に使っている棒が短く、手慣れてくるとぶら下げたまま紡ぐこともあるようです。このような方法のスピンドルのことはドロップスピンドルとも呼んでいます。
また、ナバホスピンドルと呼ばれるものは、軸が長く、あぐらをかいた腿の上で軸の先端を転がすような仕組みになっています。こちらはナバホという名前で分かるように、ネイティブアメリカン(アメリカの先住民)などが使用していた方法です。
紡錘車は発掘調査報告書に記載するときなどには、台形の上辺にあたる短い辺のほうを上にして表現しています。しかし、その使用方法からみると、視覚的には不安定ですが逆にするのが適切と思われます。なぜなら、紡いだ糸を溜めていくためには、より広い面を上にした方が溜めやすいからです。では、なぜこのように表現されているのでしょうか? これは、糸を紡ぐ際にちょうどこちらの面が外(下)側になるため、より目に触れやすい部分となります。そこで、人によってはこの部分に刻み目などの装飾を施したりしていました。こうした装飾のある面を主な部分として考えたためにこちらの面を上にして表現しているようです。
下の絵は、平安時代末期の信貴山縁起(しぎさんえんぎ)という絵巻物に描かれていた糸紡ぎの場面をリライトしたものです。紙を結った女性が、桶の中の繊維を撚って紡錘車に巻き付けている様子が描かれています。左足の下に描かれている木製の道具はどうやって使っていたのかは分かりません。別の石山寺縁起(いしやまでらえんぎ)にも同様の道具が描かれているので、糸を紡ぐ際には必要な物であったことが考えられます。木製の道具は遺物として残りにくいから残念です。
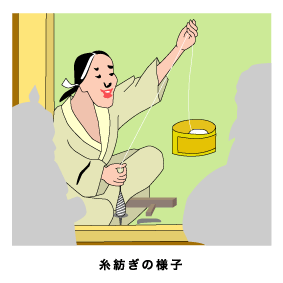
|
 |
